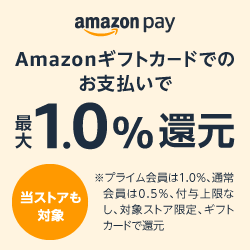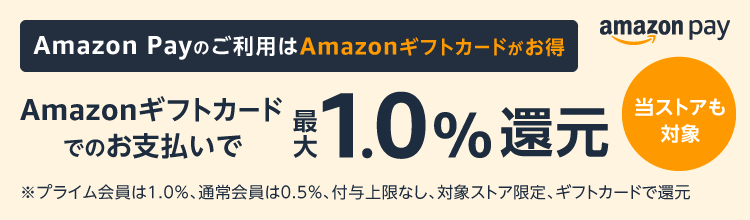ボンド塗布は不要!両面テープで貼るフローリングのリフォーム
上貼り床材 ワンフローリング
「1.8mmSPC」の施工方法
【両面テープ貼り】
既存の床に重ね貼りできるリフォーム用上貼り床材ワンフローリング。伸縮しにくく水に強いSPC製で水まわりに最適な「1.8mm耐水SPC」。両面テープを使ってフローリングの上に上貼りする方法(貼り方)を詳しく解説!


上貼り床材ワンフローリングの「1.8mm耐水SPC」は、伸縮しにくく水に強いSPC製。
1.8mm厚と薄型なので古くなった既存フローリングの上に重ね貼りが可能です。
驚くほどにカットしやすく、両面テープだけで施工OK!
ボンドの塗布が不要なので汚れを気にせず、施工時間の短縮にもつながります。
今ある床はそのままに、新しい床へとスピーディー&低コストでリフォームできます。
※床暖エリアやよりしっかり貼りたい水まわりの場合はボンドで施工してください。
-
POINT1あいじゃくりサネ仕様

フローリングに採用することで床材同士のすき間を軽減し、見た目や機能性を高める効果があります。
-
POINT2水の侵入を防いで下地を守る

サネがあることで継ぎ目から下地に水を通しにくく、既存フローリングの劣化や両面テープの剥がれを防ぎます。
-
POINT3反りが起きにくいSPC基材

反りや伸縮が起きにくいSPC基材なので両面テープでの上貼り施工が可能!※床暖エリアに敷く場合は必ずボンドで施工してください。
-
POINT4驚くほどカットしやすい

薄型フローリングの中でも抜群にカットしやすく、カッターで1、2回切れ目を入れるだけでパキッと切り離すことができます。
施工方法を動画でチェック!
施工できる場所(床下地)
について
凸凹のない下地への施工が可能です
-
両面テープ施工の場合
既存の木質フローリング等の
両面テープが接着する面※下地が防音フローリングの場合、クッション性があるため、歩行時の沈み込みによって両面テープの粘着面が部分的に剥がれ、その際に音が発生することがあります。
-
ボンド施工の場合
- 木質下地(コンパネ・合板など)
- 平らなコンクリート下地
- マンション防音フロア
- 床暖房エリア
※寸法安定性に優れた素材の為、床暖房エリアにはボンド施工のみ対応可能ですが、過度な温度変化によりわずかな伸縮が起こる場合があります。
両面テープの
接着不良を防ぐために
必ず、施工する下地の状況を
確認してください
- 段差や凹凸がないこと
(0.5mm以下) - 弓ぞりが1mm未満であること
- 不陸・起伏が1mあたり3mm未満であること
- 床なりがないこと
※浮き沈みがない場合は施工できますが、床なり自体は解消できません。 - 表面にワックス・コーティング等の油分が残っていないこと
- 化粧シートがはがれやすくなっていないこと
- 濡れていたり、高湿でないこと
(含水率14%以下) - 汚れていたり、ほこりなどが残っていないこと

- 種類別の適応下地一覧 -
| シリーズ | 1.5mm Basic |
1.5mm Smart |
3.0mm Pro |
1.8mm 耐水SPC |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工方法 | ボンド 施工 |
両面 テープ 付き |
ボンド 施工 |
ボンド 施工 |
両面 テープ 施工 |
|
| 施工可能な 下地 |
木質 フローリング |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防音直貼 フローリング |
○ | △※ | ○ | ○ | △※ | |
| 合板 | ○ | × | ○ | ○ | × | |
※防音直貼フローリングはクッション性があるため、歩行時の沈み込みによって両面テープの粘着面が部分的に剥がれ、その際に音が発生することがあります。
施工できない下地
-
- ×無垢フローリング
- ×挽き板フローリング
- ×クッションフロア
- ×長尺シート
-
- ×Pタイル
- ×畳
- ×磁器、陶器タイル
- ×石材
- ×パーチクルボード
その他の注意事項
- 目地幅が1.5mm以上のフローリングは、その上に施工すると段差や浮きの原因となるため、適していません。(※3.0mmProを除く)
- 床下からの防湿処理がされていない床には使用できません。カビの発生、接着不良、床材の変形などが起こる可能性があります。
- 床暖房パネルの上に直接貼ることはできません。施工する場合は12mm厚以上の合板を中貼りしてください。
POINT
施工に入る前の掃除は
しっかりと!
-

-
床にゴミが残っていたり凹凸があると、両面テープの接着力や床材の仕上がりに影響が出てしまう場合があります。施工前に床のゴミや汚れはキレイに取り除き、凹凸は平らにならしておきましょう。

部屋の壁が並行でまっすぐならいいのですが、特に築年数が古い場所は多少なりとも壁に歪みがあります。
壁に歪みがある場合、そのまま施工すると壁にぴったり突きつけることができず
壁際に隙間が空いてしまいます。
ここからは、壁の歪みに合わせて正確におさめるため、
1列目の床材を巾定規でカットしてから施工する方法を解説していきます。
-
準備する道具

メジャー、定規、差し金、墨つぼ(チョークライン等)
はさみ、カッター、ローラー、ペン -
使用する材料

- ワンフローリング 1.8mm耐水SPC
- 専用両面テープ
- コーキング材(必要に応じて)
施工時の温度管理について
本製品は一般的なビニール系床材に比べ、温度変化による伸縮が起こりにくい素材を使用しておりますが、わずかにサイズ変化が発生します。特に冬の寒い時期に施行したものが、夏の暑い時期や床暖房の使用によって伸長し床材が突き上げる可能性があるため、下記の事項を必ず守って施工してください。
-

-
- 施工場所の室内温度を17~25℃の範囲に保ち施工してください。(17℃以下で施工する場合は、壁際に1mm程度のクリアランスをとって施工してください。)
- 施工前に、床材を箱から出し、施工場所の温度に馴染ませてから施工してください。
- 寒冷期に床暖房設備のある場所へ施工する場合は、床暖房を使用した状態で施工してください。
- 寒暖の温度差が著しい場所への施工はお控えください。
直射日光の当たるエリア、温度変化の激しい部屋への施工は床材の伸縮が発生します。
極端に床の温度が高くなる可能性のある環境(例えば、不在の部屋で夏に直射日光が当たる場所、暖房が局所的に当たり続ける場所など)への施工は、壁際に、お部屋のサイズの約0.3%ほどのすき間を確保し、すき間が気になる場合は床用コーキングで充填してください。
採寸・割り付け
床材の割り付けは、列ごとに半分ずらす
「レンガ貼り」で貼っていきます。
-

まず、部屋の縦横寸法をmm単位で測り、割り付けを行いまます。※できるだけ下地のフローリングと目地が重ならないように割り付けましょう。
-

採寸した部屋の寸法を元に、まず、床材が何列分になるか、最後の列の幅は何mmかを算出します。
1.8mm耐水SPCの幅:152mm -

「1.8mm耐水SPCフローリング」は、あいじゃくりサネ仕様のため、必ず部屋の端から貼り進めます。※部屋の中心から貼ることができません。
POINT
できるだけ下地の目地と重ならないように割り付けすることを推奨します。
1.8mmSPCは相じゃくりのため、目地の凹凸による影響を受けにくいですが
気になる場合は、下地の目地をパテ埋めすることで解消できます。
最後の列に入る床材の幅が
極端に狭くなる場合
必要に応じて1列目の幅を
カットして調整します。
※幅カットについてはSTEP3で解説します。
例)部屋の奥行寸法が
3060mmの場合の割り付け
1列目の幅をカットし、
最初と最後の列幅を均等にする。
1列目の基準線を引く
-

STEP1で採寸した部屋の奥行寸法をもとに、部屋の中心線を出してから、始めの1列目を置く目安となる基準線を引きます。割り付けた寸法を、必ず中心線から測って印を付け、墨つぼ(チョークリール)等を使って線で結びます。
-

基準線までの寸法の出し方ですが、先ほどの割り付けを例にした場合、中心線から基準線までは19列÷2=9.5列分になるので、152mm×9.5=1444mmとなります。
1列目をカットする
-

STEP2で引いた基準線に沿って1列目になる床材を仮置きしていきます。
-

1枚目を、はめ込み受け手の白いサネ部分が右側と手前になるようにして、奥の辺を基準線に合わせ、左の壁に突きつけて置きます。
-

2枚目も基準線に沿わせ、1枚目のサネ部分に真上からぴったり合わせて置きます。
-

3枚目以降も同じように、右端の壁際に入る最後の1枚の手前まで(カットせずに置けるところまで)並べていきましょう。
POINT
壁際に入る最後の床材が
極端に短くなってしまう場合は、
スタートの1枚目をカットして調整します。
-

列の最後の1枚に必要な長さをメジャー等で測ります。壁の歪みを考慮して必ず上下2ヶ所を測ってください。
-

必要な長さ2ヶ所に印を入れ、線で結んでカッターで切れ目を入れてカットします。
-

カットした切り口は、必ず壁側になるようにして置きましょう。(使わなかった余りは、次の列の1枚目に流用できる場合があるので捨てずに置いておきましょう。)
-

1列目になる床材を基準に合わせて敷くことができたら、端材で作った「巾定規」を使って、壁に合わせて必要サイズに幅カットしていきます。
端材を使った「巾定規」の作り方
-

-
巾定規は、部屋の形状や壁の凹凸に合わせたカットができる便利ツールです。
今回は材料の床材を使います。まず、同じ材料で15cm程度の端材を用意します。床材の寸法ぴったりに合わせるため、長辺のサネ(表から見て出ている部分)をカッターでカットして取り除きます。サネ部分はカッターで切り離しが可能です。
-

用意した巾定規の裏面を上に向け、縦横の向きが同じになるように注意して、カットする床材の上に置きます。
-

奥の壁にぴったり突きつけたまま、巾定規に沿って鉛筆などで線を引いていきます。
-

巾定規が壁から離れないように滑らせながら、ズレないように線を引きましょう。※巾定規はこのあとの施工でも使用するので捨てずにとっておきましょう。
-

1列目になる床材すべてにカット線の印が入ったら、床材の位置が入れ替わらないように番号を振り、順番に重ねて一旦取り外します。
下地に両面テープを貼る
-

両面テープは、まず施工場所周囲の壁沿いに貼ります。
-

両面テープ同士が重ならないように貼りましょう!
-

周囲が貼れたら、STEP2で引いた基準線がテープの中央を通るように(1列目と2列目の間)貼ります。
-

この時も、両面テープ同士が重ならないように貼りましょう!
-

STEP3で作った巾定規を、貼り終えた1列目と2列目の間のテープ端に合わせて置き、2列目と3列目の間にも貼っていきます。
-

床材にテープを沿わせながら、手前のテープと平行になるように意識しながら貼り進めましょう。
-

次に、床材短辺の継ぎ目部分を固定するためのテープを10cmほどの長さで貼っていきます。
-

割り付け通りに床材を仮置きすると、継ぎ目の位置がわかります。
-

ハサミでテープを10cmほどにカットして継ぎ目位置が中央にくるように貼ります。
-

ここではわかりやすく説明するため、両面テープを2列目まで施工できる状態まで貼り、床材を貼り始めます。
両面テープに貼りながら
施工していく
-

まず、1列目を貼れる分だけ、両面テープの剥離紙を剥がします。
-

STEP3でカットした1列目の床材を順番通りに壁に突きつけて並べていきます。※必ず、カットした面(切り口)が壁側にくるように置きましょう。
-

貼り付け後は、ローラーで押えてしっかり圧着しましょう。
-

左隣りのサネに合わせて、短辺の継ぎ目がしっかり揃うようにして、1列目を貼っていきます。この時、手前側がまっすぐ貼れていることを確認してください。
-

1列目が貼れたら、2列目を貼る前に短辺継ぎ目と次の列の両面テープを貼っておきます。
-

2列目を貼る分の両面テープ剥離紙を剥がして、前列の長辺サネにぴったり合わせて貼っていきます。
-

短辺のサネもズレないように手前がまっすぐになっていることを確認しながら貼り進め、ローラーでしっかり圧着しておきましょう。
-

2列目最後の床材も、1列目同様に長さを測ってカットしておさめます。(※次のSTEP6で詳しく説明)
-

3列目以降も同様に、短辺の継ぎ目と、次の列の両面テープを貼ってから施工していきます。
-

※端の剥離紙だけ剥がして床材を敷き、あとから残りの剥離紙を引き抜く方法もあります。(※現場判断により貼り方は異なる場合があります。)
壁際の床材をカットしておさめる
-

まず必要な床材の長さを2ヶ所測ります。
-

カットする床材に2ヶ所印を付けます。
-

差し金を当てて印に沿ってカッターを通します。
(1回通して筋がつけばOK) -

軽い力でパキッと簡単に切り離すことができます。
-

カット面(切り口)を必ず壁側に向けて入れ込みます。
-

ローラーでしっかり貼り付けましょう。

あとは、この工程を繰り返して同様に貼っていけばOK!
幅カットが必要な壁際最後の1列の手前までどんどん貼っていきましょう!
最後の列を施工する

-

残りが壁際の1列になるまで貼れたら、最後の列に入る床材をカットしていきます。
※この時、壁際の剥離紙はまだ剥がさずそのままにしておきましょう。 -

まず、カットする床材を手前の列の1枚にぴったり重ねて置きます。
-

1列目同様に、巾定規を奥の壁にぴったり突きつけたまま、巾定規に沿ってカット線を引き、
-

線に沿ってカットできたら、両面テープの剥離紙を剥がして、カットした辺が壁側へ向くようにして、サネを合わせて貼り付けます。
-

同様に最後の列をおさめて、ローラーでしっかり圧着しましょう。
-

部屋全体に貼れました。
(※壁際の隙間が気になる場合は、コーキングで仕上げてください。)
施工完了!

© 2025 RESTA. 無断転載を禁じます。All rights reserved.
おすすめコンテンツ
PICK UP CONTENTS