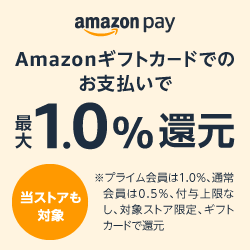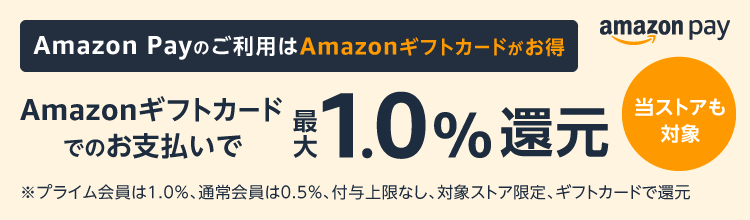柄物壁紙の貼り方のポイント生のり付き壁紙の貼り方
【柄物壁紙編】
柄物壁紙も簡単にDIYできるんです!壁の1面を柄物壁紙にするアクセントクロスがあるだけで部屋がよりオシャレに見えますよね。柄合わせと壁紙の継ぎ目処理のジョイントカットさえマスターすれば、インテリアをもっと自分らしくイメチェンすることができますよ!柄物壁紙の貼り方を詳しくみていきましょう。
壁紙を貼る前の準備
-

-
- 脚立
- カッター替え刃
- メジャー
- ハサミ
- スクレイパー
- バケツ
- サンドペーパー
- カッター
- ジョイントコーク
- スポンジ
- ドライバー
- 地ベラ
- 糸/5円玉/押しピン
- ハケ
- 鉛筆
- ローラー
- パテ
-

-
家具などは部屋の外に移動させ、作業しやすいスペースを確保しましょう。重たくて動かしにくいものは部屋の中央に集め、シートなどをかけて養生してください。コンセントカバーやスイッチプレートなど、取り外しができるものはすべて外しておきます。
コンセントカバーの外し方
-

マイナスドライバーをコンセントの隙間に
差し込む。 -

マイナスドライバーを倒しながら少しずつカバーを外す。
-

プラスドライバーでねじを外し、カバー台を外す。
※複数カ所外す場合は、1カ所分ずつマスキングテープなどでまとめ、
どこに付いていたか分かるように印などを付け、箱などに保管しておきましょう。
柄物生のり付き壁紙の貼り方

古い壁紙をめくろう
-

壁の四隅に入れ込まれたコーキングにカッターで切り込みを入れていきます。下地まで切ってしまわないように注意しましょう。
-

巾木や廻り縁がある場合は壁紙との境目に切り込みを入れます。1面のみの貼り替えの場合、貼り替えない壁紙が傷つかないように注意しながら切り込みを入れましょう。
-

壁紙の境目を見つけましょう。その境目の床側から下地と壁紙の間にカッターの刃を滑り込ませ、めくり口を作ります。
-

めくり口から壁紙を立ち上げるように壁紙を剥がしていきます。
-

途中で壁紙がちぎれてしまったら、下地を削らないように注意しながらカッターの刃を下地と壁紙の間に滑り込ませ、めくり口を作りながら剥がしていきましょう。
-

壁紙をめくると、薄い裏紙が壁に残るようになっています。壁紙の古さや、剥がし方によっては裏紙までめくれて、下地が見えてしまうことがあります。その場合は下地処理が必要になります。

壁紙のカットをしよう
-

-
ワンポイント!
床に壁紙を広げて作業します。床が汚れていると、壁紙の表面が汚れてしまいます。壁紙を床に広げる前に床をきれいにしておきましょう。養生シートなどを広めに敷いて作業してもOK!
-

床から天井までの長さを測ります。巾木や廻り縁がある場合は、その間の長さを測ります。
-

柄が見えるように床に広げ、測った長さに切りしろ分の10cmを足した長さよりも短くならない所で柄の位置を決めます。
-

先ほど決めた位置で壁紙をカットします。この1枚目が残りの壁紙のカット基準になります。
-

1枚目の柄に合わせ、以降の壁紙をカットしていきます。横に並べながら作業してもOK!
柄の位置の確認方法

壁紙は柄のパターンが縦につながっています。その柄パターンの長さを「縦リピート」といい、柄付き壁紙の場合、柄パターンの始まりを合わせて貼る必要があります。
壁紙の長さにばらつきがあっても、柄パターンの始まりが横一列にまっすぐ配置され、切りしろ分の10cmを含めた必要な長さ分あるようにカットできていればOKです。
-

柄リピートの区切りは壁紙のミミに横向きの三角や矢印で示されています。この印を合わせて壁紙を並べることで、柄を合わせることができます。また、縦向きの矢印は柄の向きを示しています。縦向き矢印の向く方向が天井側になるように貼り進めていきましょう。
-

【バックフィルムの矢印について】
裏返した状態でも壁紙の方向を合わせられるように、壁紙のバックフィルムには矢印が書かれていますが、この矢印は、壁紙の柄の天地とは関係ありません。
カット後の壁紙の向きを揃えるための目印としてご利用ください。
柄の天地(柄の向き)に
ついてのご注意
柄の天地は、壁紙表面の端(ミミ)にある矢印の向きでご確認ください。
※バックフィルムの矢印は、壁紙の柄の天地とは関係がありません。
※両端の水色とオレンジ色のテープも、商品によって左右が異なる場合があるため、柄の天地の確認には利用できません。

壁紙をたたんでいこう
-

-
バックフィルムが上になるよう壁紙を置き、フィルムを内側に巻き込むように丸めながら剥がしていきます。
この時、壁紙の端をめくり、表面の矢印で壁紙の天地(柄の向き)を確認しておきましょう。
壁紙の畳み方
-

貼った時に床側になる端を10cm折りたたみます。(柄の向きを表す矢印が向く反対側の端)
-

折りたたんだ所を上に40~50cm立ち上げ、前方に寝かせます。
-

立ち上げた長さの半分くらいの長さから折り曲げ、最初の折り目と床に置いた壁紙の端を合わせるように折りたたみます。
-

折り目を合わせて持ち、先ほどと同じように40~50cm立ち上げ前方に倒します。
-

持った折り目と床に置いた壁紙の端を合わせるようにして折りたたみます。この工程を繰り返しましょう。
-

残りの壁紙の長さが30cmほどになったら、壁紙の端を持ち、折りたたんだ壁紙の上にかぶせます。
-

-
全部の壁紙を折りたためたら、乾燥を防ぐためにビニールなどにくるんで、作業の邪魔にならない場所に移動させておきます。

基準線を引こう
-

ミミ付き壁紙の場合は貼り始めの壁際に切りしろを取ります。壁紙の巾(92cm)から切りしろ分の5cmを引いた長さの巾の位置に基準線を引きます。
-

糸の端に押しピンと5円玉を取り付けた「下げ振り」を作ります。下げ振りを使うと簡単に垂直のラインを引くことができます。
-

壁の右端から壁紙の巾より5cm短い長さのところに印をつけます。このときできるだけ天井の近くに印をつけましょう。下地の継ぎ目と印の位置が重なってしまう時は、印の位置を4~5cm右にずらします。
-

印を付けたところに下げ振りを取付けます。糸の揺れが止まったら、手でそっと押さえ、糸が動かないようにします。
-

糸に沿って10~15cmおきに印を付けていきます。下の方まで印を付けたら、下げ振りを外します。

1枚目を貼ろう
壁紙の持ち方
折りたたんだ壁紙の最後にかぶせた部分が天井に向くように持ち、壁紙の端を人差し指と親指でつまみ、そのほかの指で折りたたんだ壁紙全体を支えます。貼り付ける時は支えている指を開いて、壁紙を上下に軽く振り、壁紙を広げます。柄の天地は、壁紙表面の端(ミミ)にある矢印の向きで確認してください。
※両端の水色とオレンジ色のテープは、商品によって左右が異なる場合があるため、柄の天地の確認には利用できません。
-

天井側に切りしろ分5cmを取り、左側を基準線に合うように貼り付け、壁紙をたるませるようにして右端を仮貼りします。
-

基準線が見えやすい位置に脚立を移動し、基準線に壁紙の左側がぴったり合うように手の平で押しながら壁紙を滑らせ、位置を調整します。
-

左端の上半分の位置が決まったら、動かないように撫でバケで上から撫でつけ、押さえます。
-

右側の仮貼りした端をゆっくり立ち上げるように剥がします。次に壁紙の中央を横に撫でバケで撫でつけます。
-

次に壁紙の中央から天井に向かって縦にハケで撫でつけ空気を抜きます。基準線側から壁側に移動するように撫でつけていきましょう。
-

下半分も同じように床側に向かって撫でつけていきます。空気が入ったり、しわができた場合は、右端から壁紙をゆっくり立ち上げるように剥がし、再度同じように撫でつけます。
-

床のあたりまで壁紙が貼れたら、床に当たる壁紙の折り目を広げ、床側に向かって撫でバケで空気を抜きます。
-

最後に天井・床・右の壁際を撫でバケでしっかり圧着しておきましょう。

切りしろをカットしよう
-

天井側・床側・右の壁紙際にヘラを使って筋目を付けます。角にしっかりと壁紙が入り込むように筋目を付けると壁紙のカットがきれいにできます。
-

筋目を付けた所に地ベラをしっかりと押し当て、地ベラに沿ってカッターを入れてカットしていきます。
カットのポイント!
-

地ベラとカッターの刃は壁紙を貼った側の壁に沿わせながら、地ベラで壁を押すようにしっかりと地ベラで押さえこみます。
-

カッターの角度はなるべく寝かせて持ち、切れ味を保つためにこまめにカッターの刃を折って使いましょう。
-

カットが終わったらカットした端にローラーをかけてしっかりと押さえ、濡らしたスポンジではみ出したのりをしっかり拭き取ります。
-

のりの拭き取りが終わったら壁紙の左側のテープを引き抜き、壁紙の浮きを撫でバケで撫でつけて押さえます。

2枚目以降を貼っていこう
-

-
ワンポイント!
無地の壁紙の場合は柄合わせの作業は不要ですが、壁紙のミミに矢印が付いている場合は自然な仕上がりに施工するために、横向きの矢印の高さを合わせて貼りましょう。
-

壁紙の右端が1枚目の壁紙の上に3cm重なるように貼り付けます。この時、壁紙のミミに付いた横向きの矢印の高さが合うように貼り付けましょう。
-

左側は壁紙をたるませて仮貼りします。壁紙同士の重なりがよく見える位置に脚立を移動させ、壁紙の上半分の柄を合わせます。
-

壁紙の上半分の柄合わせが終わったら、左側の仮貼りした端をゆっくり立ち上げるように剥がし、壁紙の中央を横に撫でバケで撫でつけます。
-

2枚目以降は1枚目と逆の方向に撫でバケを動かし貼り進めていきましょう。
-

下半分も同じようにして柄合わせを行いながら貼り進めたら、天井側・床側の切りしろをカットします。

ジョイントカットをしよう
-

上にかぶさった壁紙のミミから5mmほど内側の場所に地ベラを当て、カッターの刃を壁に垂直に当て、角度を寝かせて持ちながら重なった2枚の壁紙を天井から床までカットします。
-

上に重なった壁紙のミミを取り、重なった壁紙の天井側を少しめくり、裏の残ったテープと下の壁紙の耳を取り除きます。
-

余分な所が取り除けたら継ぎ目を撫でバケで撫でつけ、その後ローラーでしっかりと押さえます。
-

はみ出したのりをふき取ります。天井や床側についたのりもきれいに拭き取りましょう。

3枚目以降もどんどん貼り進めよう
生のり付き壁紙の豆知識
-

上下のカットをする前に壁紙の左右の端の柄の高さが合っているか、その都度確認しながら進めます。
-

ヘラで筋目を入れる段階で柄を確認し、柄の高さが合っていないようなら、壁紙の位置を調整し、柄の高さを合わせましょう。
-

高さが合っていないまま貼り進めてしまうと、柄が斜めになったり、切りしろが取れなくなったりして、仕上がりが悪くなります。
-

柄の高さに気を付けながら、3枚目以降も同じようにして残りも貼り進めていきましょう。
-

角部を巻き込んで貼る場合の施工方法はこちら!

最後の壁紙を貼ろう
-

左端の壁から、右に貼った壁紙の左端のミミまでの長さを測ります。
-

測った長さに、左側の切りしろ5cmと継ぎ目部分の3cmを足した長さでカットします。貼った時に右側になる方の端が残るようにカットしましょう。
-

-
カットするときの注意ポイント
紙の継ぎ合わせのために壁紙の右側を残します。柄付きの壁紙は、壁紙の左側と右側の柄が合うように柄がプリントされているため、右側を切り離してしまうと柄合わせができなくなります。
-

これまでと同じように壁に貼り付け、天井側・床側・左の壁際にしっかりとヘラで筋目を付けます。筋目が付けれたら、上下の切りしろをカットしましょう。
-

最後に左側の切りしろをカットします。筋目に地ベラを押し当て、壁紙を貼った方の壁に地ベラを添わせるように押し付けカットしていきましょう。
-

右利きの人の場合は地ベラを持つ手の下からカッターを持つ手をくぐらせるようにしてカットします。そうすることでカッターの刃の角度が保ちやすくなります。
-

カットが終わったらカットした端にローラーをかけてしっかりと押さえ、はみ出したのりをふき取りましょう。

壁紙の施工道具
-
【初級向け】 初めてのDIYに!

ステンレスカット定規、押さえハケ、ローラー、ヘラ、カッターの5点がセットでお得に。生のり付き壁紙と同時購入なら、道具セットは送料無料でお届けします!
※壁紙のご購入が10m未満の場合、壁紙分の送料は別途ご請求させていただきます。税込902円 -
【中級向け】 プロも使えるセレクト道具!

デザイン・品質・価格・使いやすさにこだわり、プロの職人も認めるワンランク上の道具をセレクト!壁紙貼りに必要な道具が、お得な価格で一通り揃います!DIY中級者や上級者(セミプロ)、プロの方にオススメです。
税込2,915円
-
ハケとヘラの役割を
マルチにこなす便利な道具も!
-
汎用スキージー
壁紙の施工道具として1つあると便利!これ一つで、空気抜きやシワ伸ばしはもちろん、角部の折り込み、カット定規など、様々な用途で使える汎用スキージーです。
税込462円
壁紙施工の関連商品
-
壁紙の下地処理や、貼る前の補修が必要な場合は補修材&下地処理材をチェック!下地の小さな穴を補修するミニマルパテや、下地に亀裂が入っている場合に補強できるファイバーテープなどが揃っています。
-
業者様向けに、お得な価格でまとめ買いできる副資材や、施工に必須のアイテムをピックアップしました。ヒビ割れ補修用のファイバーテープや、壁紙の穴の補修に使えるリペアプレート、小さなサイズのミニマルパテなどが揃っています。
壁紙 おすすめコンテンツ
PICK UP CONTENTS