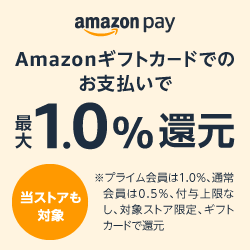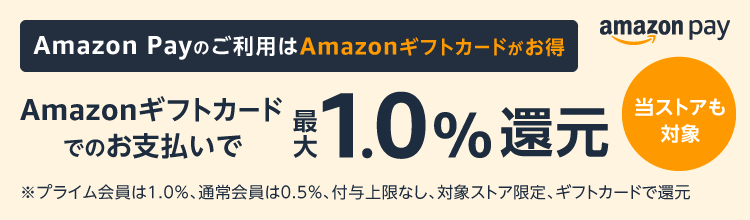一般的なフローリングの一番上の層にMDFが使用されています
フローリングに使用される
MDFの種類と検証
日本の住宅において、一般的に「フローリング」と呼ばれている床材の表面部分には、MDF(中密度繊維板)が使用されていることが非常に多くあります。このMDFの種類や品質は、そのフローリングの性能、特に耐久性や耐水性、加工性などに大きな影響を与えます。そのため、MDFの特性を理解することは、適切な製品選びや設計において重要なポイントになります。
なぜMDFがフローリングに
使用されるのか
小さな鉄球を1mの高さから
落としたときの凹みの差

日本の住宅でよく使われるのは、総厚12mmの「複合フローリング」と呼ばれる製品です。この複合フローリングは、市場に出回り始めた当初、ラワンという木材を使用した合板の表面にシートを貼り付けた構造が主流でした。
しかし、ラワン合板の価格高騰や国産材の積極活用を推進する動きから、杉やヒノキといった針葉樹系の国産合板が使われるようになりました。ただし、針葉樹合板はラワン合板に比べて柔らかく、フローリング用途としては「凹みに弱い」という大きな弱点がありました。
この課題を解決するために、針葉樹合板の上にMDF層を重ねた構造が登場しました。これにより、加工しやすく、強度も確保しやすくなり、コスト面でも優れたフローリングが開発されました。現在では、このような構成をもつ複合フローリングが主流となり、市場シェアの大半を占めています。
実際に同じ高さから鉄球を落として凹みの差の実験を行いました。
杉(針葉樹)の板が凹んでいるのに対して、最も弱いユリア樹脂針葉樹タイプのMDFでも全く凹みは発生しませんでした。
複合フローリングの構造
一般的な複合フローリングの
表面シートを剥がした状態

日本国内で流通しているフローリングの規格は、一般的に12mm厚で設計されています。この中で、MDF層は約2.7mmを占めています。
実際のところ、MDF層は1.0mmや1.5mmの厚さでも表面材としての機能を果たすことができます。しかし、2.7mmという厚さが採用されているのは、MDF素材の工業的な生産性の高さとコストパフォーマンスのバランスによるものです。製造時の安定性や機械加工性も考慮されており、「作りやすい厚み」として標準化されているのです。そのため、必要以上に分厚くなっているという点はあります。
一般的なMDFとは
実際にホームセンターで
販売されている「普通MDF」

MDF(Medium Density Fiberboard:中密度繊維板)は、日本工業規格(JIS A 5905)において繊維板の一種として定義されており、インシュレーションボード、MDF、ハードボードの3種に分類されています。
さらにMDFは用途や性能に応じて「普通MDF」と「構造用MDF」に分類されます。フローリングに使用される種類は「普通MDF」が一般的で、「構造用MDF」はそれ自体が建物を支えるようなかなり強度が必要なところに使用されます。フローリングの表面としては、そこまでの強度は必要ではないため「普通MDF」が主に採用されています。
MDFの弱点~水分~
普通MDFに水分を滴下し放置すると
MDFに膨らみが発生する

MDFの最大の弱点は、水分への耐性です。木材の繊維を樹脂で圧縮・成形した材料であるため、湿気や水分を吸収しやすい特性があります。水分を吸収すると、MDFは膨張して変形しやすくなり、これがフローリング表面の「膨れ」や「浮き」の原因となります。
さらに、膨張したことで表面に貼られた化粧シートが剥がれるリスクも生じます。もちろん、日常的な水こぼし程度であればすぐに拭き取ることで問題を防げますが、放置したり、常に湿気がこもるような環境にある場合は、吸湿が進行し、劣化を早めてしまいます。
色の違いで分かる 木材の種類
-
針葉樹のMDF
水分を吸いやすい
-
広葉樹のMDF
水分を吸いにくい
木材として入手しやすい針葉樹は、成長が早く、比較的安価に手に入る点が特長です。しかしその一方で、成長が早いぶん木材の密度は低く、内部に空隙が多く含まれています。つまり、水分を吸収しやすい構造であるということです。
このため、防水性という観点から見ると、針葉樹よりも広葉樹のほうが明らかに優れた性能を持っていると言えます。
一般的に、フローリングの表面層に使用されるMDFには、針葉樹由来のものは用いられず、すべて広葉樹MDFが使用されています。
実際に複数のフローリングの断面を調べたところ、いずれも濃い色味の広葉樹MDFが使用されていることが確認できました。
見た目でわからない 樹脂の種類
-
広葉樹のユリア樹脂MDF
水分を吸いやすい
-
広葉樹のメラミン樹脂MDF
水分を吸いにくい
MDFを成形する際に使用される接着樹脂には、主に「ユリア樹脂」と「メラミン樹脂」の2種類があります。見た目では全く差はありません。
ユリア樹脂は比較的安価で加工性に優れますが、耐水性に劣り、ホルムアルデヒドの放散量も高めです。一方、メラミン樹脂は高い耐水性と低ホルムアルデヒド放散が特徴で、品質面でも優れています。
さらに、より高性能な「ウレタン系樹脂」を用いたMDFも存在します。これはホルムアルデヒドを含まず、耐水性・耐久性において非常に優れていますが、その分コストが高くなるため、用途によっては採用が限定される場合があります。 フローリングでは一般的にメラミン樹脂のフローリングが使用されています。
露出部の防水処理
-
水がMDFに触れない構造の例

Classen社 megaloc aqua protect仕様の場合
- (1)ワックスによる処理
- (2)ペイントによる処理
- (3)目地部分を重ねる構造
-
実際に接合部に水をかけた実験

Classen社の実際のフローリングに水をこぼし乾燥まで放置⇒目地からの吸水による水分膨張を見られませんでした(全ての状況で膨張しないことを保証するものではありません)
フローリングにしたとき、表面はフィルムなどで覆われているため、水分が染み込むことはありませんが、フローリングの断面や目地部分などはMDF基材が露出する場合があります。この露出部分に防水ワックスなどを塗布し、基材にふれた水分が吸水しないための工夫などがあります。ワックスの他にニスやウレタンコーティング処理、着色塗料の塗膜による防水処理などがあります。
JIS規格における
「MDF素材」としての
耐水レベルの定義
試験基準 ※簡素化して記載しています。 |
耐水レベル | ||
|---|---|---|---|
| 普通 (Uタイプ) |
耐水1 (Mタイプ) |
耐水2 (Pタイプ) |
|
|
湿潤時曲げ強さ A試験 約70℃の水に2時間水浸し、その後曲げ強度を標準状態(乾燥状態)の合格強度と比較する |
- | 50%以上 | - |
|
湿潤時曲げ強さ A試験 約100℃の水に2時間水浸し、その後曲げ強度を標準状態(乾燥状態)の合格強度と比較する |
- | - | 50%以上 |
|
吸水率試験 約20℃の水に24時間水浸させ、水浸前と後の厚さの差を測定し、膨張率を測定する |
- | 17%以下 | 17%以下 |
JIS A 5905において、MDFの耐水性能は以下の3段階に分類されています。
普通(Uタイプ)
耐水1(Mタイプ)
耐水2(Pタイプ)
このうち、フローリングに求められるのは耐水性をもつ「Mタイプ」が多く使われています。
湿潤時曲げ強さの試験は主に構造材料として重要ですので、フローリングとして重要な試験は吸水率試験です。
すなわち、「Pタイプ」は強度を求められる構造用材料として使われていることが多いです。
MDFの使用する
位置によって変わる強度

MDFは成形時に圧力がかかる面(上下の表層)が特に高密度になり、この部分を「岩盤層(がんばんそう)」と呼ぶことがあります。
MDFの内部は、表層部(岩盤層)と中心部(中間層)に分けられ、これらでは密度や強度が異なります。中間層はやや密度が低くなりがちで、耐衝撃性や耐水性にも違いが生まれます。しかし、厚さ2.7mmのMDFの場合、中間層がほとんど存在せず、ほぼすべてが岩盤層で構成されているため、フローリングの表面材として非常に適しています。
MDF素材の耐水実験をしました
耐水実験方法

実際に市場で使用されているMDF素材を対象に、耐水性の比較実験を行いました。それぞれの素材の表面を軽く研磨し吸水性を高めた状態で24時間水に浸し、その後の厚みの膨張率を測定しました。
※JISによるMDFやJAS規格によるフローリングの試験方法とは異なります。
-

-
針葉樹系・ユリア樹脂タイプ
- 実験前厚み:2.52mm
- 実験後厚み:3.461mm
- 膨張率:37.3%
いわゆる普通MDF。かなりの水分膨張が発生しました。
仮にフローリングの表面材として使用し、水をこぼした場合表面フィルムの剥がれなどが発生する恐れがあります。
-

-
広葉樹系・ユリア樹脂タイプ
- 実験前厚み:2.79mm
- 実験後厚み:3.20mm
- 膨張率:14.9%
試験後の水が最も濁りました。これはユリア樹脂が弱く、広葉樹の濃色の成分が抽出され安かったためと考えられます。水分の膨張率の規格合格値以内ではありますが、余裕のない数値であるため、あまりフローリングに適していないと言えるでしょう。
-

-
広葉樹系・メラミン樹脂タイプ
- 実験前厚み:2.75mm
- 実験後厚み:2.99mm
- 膨張率:9.0%
フローリングに使用されているタイプのうち、より高い防水性をもつ耐水2「Pタイプ」です。今回の試験のうち、もっとも優れた低い膨張率でした。
-

-
クラッセン MANOR(通常HDF)
- 実験前厚み:3.83mm
- 実験後厚み:4.72mm
- 膨張率:23.2%(JAS合格基準値:25%)
針葉樹90%、広葉樹10%素材のHDF素材。
実験後もただ一つ水中に沈まなかった材料です。
ただし、膨張率は最も高い結果となりました。フローリング製品としては、露出部分にワックス処理が施されており、そもそも水分が基材に触れない処理がされています。
-

-
クラッセン HYDROCLICK(高耐水HDF)
- 実験前厚み:3.64mm
- 実験後厚み:4.42mm
- 膨張率:21.5%(JAS合格基準値:25%)
最も高密度であるMDF。実験初期からほぼすべてが水に沈み、その密度は970mg/Lとほぼ水と同じ比重尾を持っています。クラッセン社の中で、防水能力が2番目に高いMDF素材です。
水分による膨張率については、一般的に広葉樹よりも針葉樹の方が膨張しやすく、また、メラミン樹脂に比べてユリア樹脂の方が膨張しやすい傾向があります。
クラッセン社のMDF素材には、海外で「HDF(High Density Fiberboard)」と呼ばれる、一般的なMDF(Medium Density Fiberboard)よりも高密度な素材が使用されています。
このフローリングには、表面層だけでなく全層にわたりHDFが使用されており、フローリングとしての十分な強度を確保するためにMDFではなくHDFが採用されています。
全層がMDF(またはHDF)で構成されているフローリング製品については、材料としてのJIS規格(工業規格)ではなく、製品全体に対するJAS(日本農林規格)に基づいて性能が定義されています。JASにおける膨張率の合格基準値は「25%以下」とされています。
なお、今回の実験では基材部分のみを対象に試験を実施しましたが、JAS試験では表面および裏面の防水層を含めた状態で評価されるため、実際の膨張率は今回の結果よりも低くなることが予想されます。
MDFフローリングは
温度変化には強い
-

-
MDFは木質で、フローリング素材として対極にあるのが樹脂素材です。一般的に、炭酸カルシウムに塩ビを接合するための樹脂として用いられることが多いです。その樹脂製フローリングは、耐水性は優れますが、温度変化による素材の寸法変化が、MDFに比べて何倍も大きいというデメリットがあります。
水回りやランドリールームなどには樹脂製フローリングのほうが性能を発揮しやすく、快適性が求められる居室空間においては、MDFフロアは最適なフローリング素材の一つです。
その中には原状回復が可能なボンドを使用しないクリック式フローリングもあります。
まとめ
一般的なMDFとフローリングに使用されるMDFの違いについて説明しました。実際、国産の複合フローリングのMDF素材の提供元はかなり少なく、使用されているMDFも基本的に同じであるため、販売されている複合フローリングのMDF層には大差はありません。一方、海外では表面層だけにMDFを使用することは少なく、クリック式のフローリングである場合、MDFよりもベースとして強固なHDFが使われることが一般的です。そのため、海外製のクリックフローリングと日本製の複合フローリングとでは、基材の密度や耐久性に違いがあることを理解しておく必要があります。とくに耐水性や寸法安定性といった性能は、使用される基材の品質に大きく左右されるため、単に表面デザインや価格だけでなく、MDFやHDFといった内部構造にも目を向けることが重要です。
フローリングを選ぶ際には、見た目や価格に加えて、「中に使われている素材がどのようなものか」まで考慮することで、より納得のいく選択ができるようになるでしょう。
引用規格
日本工業規格 JIS A 5905:2022「ビニル系床材」
日本工業規格 JIS A 5905:2022 「繊維版」
日本農林規格:フローリング
© 2025 RESTA. 無断転載を禁じます。All rights reserved.