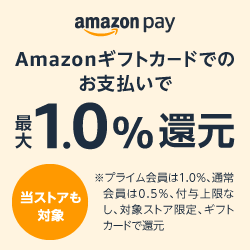天然木ウッドデッキDIY施工方法を詳しく紹介!
天然木ウリン ウッドデッキ
施工キットの組み立て方
天然木ウリンは、重厚かつ強度があり耐久性・耐水性・耐腐朽性に優れ、デッキ材としても人気の高い樹種ですが、素人が施工するには難易度がやや高め。RESTAのウッドデッキ施工キットなら、カットされた材料と専用ビス・専用ビット等がセットで届くので施工しやすくDIYにもおすすめです。
-


束・大引・根がらみ・幕板・床板が仕上がりの規格サイズにジャストカットしたサイズで届くので、難易度の高い切断作業が不要です。
-


下穴の位置が分かるように、材料にはあらかじめ浅く下穴が開いているので、下穴の位置決めが不要で作業の手間を軽減できます。
-


硬質ハードウッド用デッキビス2種と、専用の□型ビット、下穴・皿取加工用のドリルビット3種が付いてくるので準備しなくて済みます。
このページでは、
出幅(奥行)989mm×間口1,800mm
の
施工キットを使ったウッドデッキの
組み立て方を紹介します。
準備する道具・使用する材料
-
準備する道具

電動ドライバー(※14.4V以上推奨)
水平器、メジャー、差し金、作業用手袋
スペーサー(3mm)、サンダー(紙やすり#100)※14.4V以上のインパクトドライバーを使用すると、よりスムーズに施工できます。
※施工場所の地面が土の場合は、基礎工事が必要になるため、別途、束石(基礎石)・モルタル等をご準備ください。 -
使用する材料

【セット内容】
束柱(8本)、大引(4本)、根がらみ(2本)
幕板(3本)、床板(18本)
専用ビス(ハードウッド用ステンレス製)5×90、5×52
専用ビット(□型ビット1本)、下穴用ドリルビット3種
ドリルストッパー
-

ウリンなどの超硬質ハードウッドを施工する際は、必ず下穴が必要です。(※使用するビス径より0.7mm~1.0mm細い下穴)
ウリンデッキ施工キットは、下穴の位置が分かるように、材料にはあらかじめ浅く下穴を開けています。施工の際は、付属の錐(ドリルビット)で下地まで下穴を開けてください。皿取加工も同時に行えます。 -

材のひび割れやビスの折れ等を防ぐために、デッキビスの全長よりも5mm程度深い下穴をあけるのが重要なポイントです。
付属のドリルストッパーを使用することで、必要な深さでピタっと止めることができますので、必要に応じて使用してください。
-

-
付属のドリルビット(皿取錐)
仕様・商品規格◆仕様
適用材 : 高硬質ハードウッドデッキ材 (木材専用)
適用機種 :インパクトドライバ・ドリルドライバ 14.4V以上
適正回転数:3,000回転/分以下 / 材質:ハイス鋼
イモネジ:M4×3(内錐を固定) / 形状:六角軸 6.35mm◆商品規格
下穴 A φ4.0mm / 適用ビスサイズ φ5.0mm
皿取 B φ10.0mm / 軸径 d 六角軸 6.35mm
※止めネジ以上切り込むと、木屑が詰まり
折れる場合がございますのでご注意ください。
天然木ウリン ウッドデッキ
施工キット
の組み立て方
(施工方法)
施工場所の事前準備、束石の設置
-

-
今回は、水平なコンクリートの地面にウッドデッキを施工していきます。
※切断、下穴加工等の作業をする地面が、土間コンクリートの場合は全面にブルーシート等を敷く事で 汚れを防止できます。オガクズでも水分を含むと、樹液(灰汁)が出ますのでご注意下さい。
-

施工場所の地面が土の場合は、デッキの浮き沈みを防ぐために必ず地中埋込土台ベース工事または束石の設置工事(割栗地業・路盤基礎工事等)を行ってください。
※ウリンは水中に使用できる材木の為、束石を設置せず、地中に沈下防止の路盤基礎を作り、直接束柱を土に埋めることも可能です。
-

ウリン施工キットはGL~500㎜仕上げ仕様(束柱を地中に50mm埋め込む場合)となります。地中埋め込み土台ベースにすることで、ウリンから流れ出る樹液(灰汁)が目立たなくなるメリットがあります。
デッキの仕上り高さに応じて、ピンコロ石・平板などの束石を設置して高さを調整してください。※デッキのズレ等を防止するため、L字金具等(※別途準備が必要)で束石と束柱を固定することをお勧めします。
下穴加工(束-根がらみ・幕板)
根がらみ、幕板の取り付け作業は横向きになるため、DIYでは下穴加工の難易度が少し高くなることが想定されます。そのため、束柱を設置する前に、根がらみと幕板のビスの位置を合わせて、先に下穴加工を済ませておくと、取付時に作業しやすくなります。
-

束柱を水平な場所へ横向きに置き、根がらみと幕板の取り付け位置を合わせます。
-

ビス位置にはあらかじめ浅く下穴があいているので、付属の錐(ドリルビット5×52L用)で下地(束柱)まで下穴をあけます。(※皿取加工あり)
サイズが小さい場合はデッキ端部のみでもOK。後々の作業を考慮して必要に応じてあけてください。
束柱を設置する
※今回の施工では、水平なコンクリートの地面に直接束柱を置きます。
束石や埋め込みベースの場合も、設置する土台が水平であることが前提です。
-

図面の【束配置図】に従って束柱(70×70mm)を設置していきます。
※デッキのズレ等を防止するため、L字金具等(※別途準備が必要)で束石(土間ベース)と束柱を固定することをお勧めします。今回は束を固定せずに施工しています。
-

水平器を用いて、束柱が垂直であること、幅方向と奥行き方向に水平であることを確認します。
※束柱の設置時、図面通りの寸法になっていないとデッキ材の取り付け寸法も合わなくなり、カットが必要になってしまいます。そのため図面の寸法通りに設置できているか、念入りに確認してください。
大引を設置する
-

図面の【大引配置図】に従って束柱の上に大引(70×70mm)を設置していきます。
-

大引を束柱の上に乗せ、位置を合わせます。
大引のビス位置に、あらかじめ浅く下穴があいているので、まず、付属の錐(ドリルビット5×90L用)で下地(束柱)まで下穴をあけます。 -

次に、さきほどあけた下穴の位置に、錐(φ10mm下穴用インパクトビット)で大引の途中まで大きめの下穴をあけます。
穴の深さは、ビス(5×90)のねじ部分がほとんど束柱にかかるようになる状態が目安です。
付属のドリルストッパーを使用すると、止めたい深さでピタっと止めることができます。 -

穴の深さをビスより長くする必要があるため、再度ドリルビット5×90L用でさらに深い下穴をあけます。
-

付属の角ビット(ビット型□)をドライバーに付け替えて、付属のビス(5×90)で束柱と大引を固定します。
※片方#2(根がらみ・床板・幕板固定用)、片方#3(大引固定用)となっていますので付け間違えのないように注意してください。
-

全ての大引を固定できたら、再度水平を確認しておきましょう。

同様に全ての大引を束柱に固定して設置完了です。
根がらみを取り付ける
-

束柱の横揺れを防止するため、間口方向に根がらみ(20×105mm)を取り付けます。
根がらみを取り付けることでデッキが安定します。 -

まず、ドリルビット5×52L用で下穴をあけてから、角ビット(ビット型□)をドライバーに付け替えて、付属のビス(5×52)で根がらみを束柱に固定します。
根がらみは幕板の位置に干渉しない高さで取り付けてください。

デッキの土台部分が完成しました。
床板を張る
-

図面の【床板配置図】に従って大引の上に床板を張っていきます。
-

床板の目地幅は3mmです。
まず、3mmのスペーサーを挟みながら、全ての床材を図面の割り付け通りに仮置きします。 -

床板が大引の上にぴったり配置されることを確認できたら、手前から1枚ずつ外しながら床板に沿って目印の線を引きます。
-

目印の線に合わせながら、床板を張っていきます。
床板同士の継ぎ目は突き付けになります。
※わずかな寸法誤差により隙間があく場合があります。 -

ビス位置に、あらかじめ浅く下穴があいているので、付属の錐(ドリルビット5×52L用)で下地(大引)まで下穴をあけます。※皿取加工も同時に行えます。
-

角ビット(ビット型□)をドライバーに付け替えて、付属のビス(5×52)で床板を大引に固定します。
ビス頭が少し入るくらいが目安です。ビス頭が出る場合は、再度下穴用ビットで皿取部分を深くとって調整してください。 -

デッキの上に乗り、膝で床板を押さえながら作業すると、ズレずに固定できます。
-

どんどん張っていきます。

デッキ面が完成しました。
幕板を取り付ける
-

デッキの3方向に幕板を取り付けます。
※床板同様、ビスで固定する前に必ず、付属の錐(ドリルビット5×52L用)下穴をあけてください。 -

角ビット(ビット型□)をドライバーに付けて、付属のビス(5×52)で幕板を大引の側面に固定します。

幕板を取り付けできました。

これで、全ての材料の組み立てが完了です。
仕上げ処理・後処理・清掃
-

デッキの表面を、サンドペーパー(#100)で木目に沿ってやすりがけを行い、小さなササクレ、皿取部分のバリ、汚れ等を除去してください。
-

可能な場合は、電動サンダーでの研磨をおすすめします。作業効率が良いだけでなく、とても綺麗に仕上がります。
-

-
ビス頭がデッキ面より出ている状態でサンダーをかけると、ビスの塗装が剥げて白っぽくなり目立ってしまいますので注意してください。
ウッドデッキ完成!


天然木ウリンの
注意点・経年変化について
ウリン特有の樹液(灰汁)について
水濡れ・雨水などにより、ウリン特有のアク(樹液)が出ることがあります。ポリフェノールを多量に含有しているために発生するもので、人体に影響するものではありません。
樹液(灰汁)で、モルタル・コンクリート及び周辺部分に茶褐色の汚れが付着することがありますが、そのままの状態で半年程度すると 自然と樹液(灰汁)のシミは薄くなります。
樹液(灰汁)が付着する状況は個体差、施工場所、施工時期により異なります。 樹液(灰汁)の流出は設置後半年程度で落ち着くと言われています。
■切断や下穴加工等の作業をする地面が、土間コンクリートの場合は全面にブルーシート等を敷くことで汚れを防止できます。オガクズでも水分を含むと、樹液(灰汁)が出ますのでご注意下さい。
-

-
【束石等に付着した場合の除去方法】
水、塩素系漂白剤を1:1の割合で事前準備した容器に入れ薄め、樹液(灰汁)が付着した部分にゆっくりと数回に分けてかけていきます。数分後、樹液(灰汁)が薄くなってきます。
その後、ホースで水道水を掛けながら、準備したブラシで軽くこすります。最後は塩素系漂白剤が残らない様に流水で完全に洗い流して下さい。
その他の注意点
■天然木の為、経年変化により多少のささくれ・反りや、乾燥による表面の千割れが生じる場合があります。
ささくれが気になる場合は、#60~#120程度のサンドペーパーで除去してください。
■天然木のため、それぞれ質感・風合い(色むら・板目)に違いがあります。
また紫外線の影響により少しずつグレー色に変化しますが、強度に問題ありません。
■ウリンは無塗装でノーメンテナンスでも強度・耐久性に全く問題はありませんが、ササクレの発生を防ぎ、初期の状態を保ちたい場合には、浸透性の自然塗料などで定期的にメンテナンスすることをお勧めします。
■ウリンは非常に硬いため、加工を要する場合には電動工具が必要です。カットする場合は歯切ノコを目高くしてください。
経年変化について
ウリンは、天然木材であるが故の、紫外線や外気の温度差による収縮、色合いの変化、細かい千割れの発生など、経年変化が起こります。
-

-
【色の変化について】
ウリンは濃い褐色(黄褐色・赤褐色)をしていますが、月日が経ち雨や紫外線に当たることでシルバーグレー色に変化していきます。変色後もウリンの耐久性・強度などはそのままなので安心して使用できます。
約1年程度、色が落ち着くまで経年変化をお楽しみください。
ご購入はこちら
ウッドデッキ おすすめコンテンツ
PICK UP CONTENTS