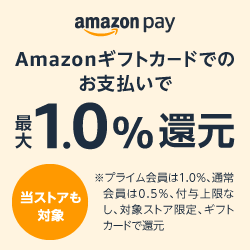後悔しない床のDIY
原状回復できるフローリングや
フロアタイルの
JIS規格にはない
選び方のポイント
原状回復が可能なフローリング・フロアタイルとして販売されている製品は本当に原状回復できるのか?いい商品を選ぶためのJIS規格には無い選び方のポイントや、避けた方が良い商品をこのページでご紹介します。
「原状回復が可能」の
言葉に注意!
-

-
原状回復が可能なフローリングは、主に樹脂系のフロアタイルが使用されます。フロアタイルは、JIS規格 A5705「ビニル系床材」において、「接着剤形」と「置敷き形」の2種類に分類されています。「原状回復が可能なフロアタイル」としての明確な定義はなく、市場では「置敷き形」のフロアタイルが原状回復できる製品として販売されています。そのため、実際の使用においてはJIS規格だけでは不十分な場合があり、原状回復を前提とする場合は注意が必要です。
貼って剥がせる
フローリングについて

貼って剥がせるタイプのフロアタイルには、いくつかのバッキングの種類があります。中でも有名なのが、「東リ ピタフィー」シリーズです。この製品は、柔軟性のあるバッキングに多数の小さな気泡を含んでおり、その気泡が吸盤のような役割を果たしてフロアタイルを下地に密着させます。
また、接着剤や粘着剤を使用していないため、剥がした際にバッキングの素材が残ることはありません。ただし、下地側のコーティング(主にワックスなど)が吸着したまま剥がれてしまい、ムラとなって現れることがあります。その場合は、再度ワックスを塗布することで元の状態に戻すことが可能です。
さらに、新しい素材としてTPR(熱可塑性ゴム)などをバッキングとして使用した製品なども登場しています。RESTAでは、さまざまな種類を試験・検証してきましたが、現時点では完璧な素材は見つかっておらず、オリジナル製品としての採用には至っていません。
マスキングテープを下地に貼る
フローリング施工は
お勧めしない
マスキングテープは常にきれいに剥がせるわけではなく、再剥離可能な期間が決まっています。その期間は製品によって異なり、3週間や3か月といったものがありますが、1年以上経過しても剥がせるマスキングテープは存在していません。
そもそもマスキングテープは、塗装時に塗りたくない箇所をカバーする目的で使用されるため、3か月以上貼り続けるような状況は想定されていません。そのため、長期間貼り付けたままにすると、粘着剤が下地に残る可能性があります。

また、マスキングテープの表面には、裏面の粘着剤が付きにくい加工が施されています。そのため、その上に両面テープを貼ると密着しにくくなります。したがって、マスキングテープの上に両面テープを貼る施工方法は、あくまでも簡易的な方法であり、多少の不具合が発生しても問題ない場合にのみ適した工法といえます。
「吸着材」が無い製品が
確実に原状回復できます。
しかし、接着剤に頼らず安定したフローリングを製造することはとても難しいことです。
ここからコンテンツの内容も少し難しくなります。
フローリング選びにおける
JIS規格とは
JIS(Japanese Industrial Standards、日本工業規格)は、日本の工業製品やサービスの品質・性能・安全性を確保するために制定された国家規格です。この規格は、製品に関わる団体や製造メーカー、ブランドメーカーが協議し、「この製品はこのように作るべき」と決めた基準に基づいています。特に消費者にとっては、「この製品を選べば目的を達成できる」という品質や性能の保証として役立ちます。
しかし、新しい製品に関しては、JIS規格の改訂が追いつかない場合や、特定の企業のみが製造しているために業界団体としての協議が行われない場合があります。その結果、優れた製品であってもJIS規格が存在しないことがあります。また、「JIS規格適合品」と表示されている製品であっても、用途に適していなければ十分な性能を発揮できず、施工不良などの原因になることもあります。
なお、木質系フローリングはJISではなく、JAS(日本農林規格)によって定義されています。
JIS規格で定義される
フローリング(樹脂系)の種類

樹脂系フローリングには、JIS規格 A5705「ビニル系床材」があります。ただし、規格のタイトルにもある通り、ビニール(PVC)を使用していない床材である NON-PVC床材(近年、世界的に普及しつつあるPVCを含まない床材)は、この規格の対象外となります。
また、このJIS規格においてフロアタイルは、「接着剤」または「粘着剤」で固定する2種類のみが定義されており、いずれも使用しないタイプの製品は規格の範囲外とされています。
つまり、原状回復が可能なフローリングに対応するJIS規格は存在しません。
しかし、実際の市場では、特性が類似している「置敷きフロアタイル」(粘着剤で施工するタイプ)を「JIS規格適合品」として販売しているケースが多く見られます。
種別ごとのフロアタイルの
特徴や用途と商品例
-
接着型フロアタイル

フロアタイルは、反りや伸縮が生じても、ボンドで完全に固定することで安定させることができます。製品自体の価格は比較的安価であり、ショッピングモールの床などに広く使用されています。
また、近年では住宅の水まわりでも採用されるケースが増えています。基本的に、土足にも対応できる耐摩耗層が備わっているため、高い耐久性を求められる環境に適しています。
-
置敷きフロアタイル

反りや伸縮率を抑えたフロアタイルは、基本的に反りを防ぐために厚く重いものが多く採用されています。粘着剤は、フロアタイル同士が横滑りしないよう固定する目的で使用されます。
このタイプのフロアタイルは、オフィスのタイルカーペットからの敷き替えや、賃貸店舗などでの使用が一般的です。
-
原状回復できるフロアタイル

既存のフローリングの上に敷くことで安定するフローリングは、下地と固定しないため、海外ではフローティング工法と呼ばれています。その特性上、施工後の安定性を確保するために、製品ごとに異なる特徴があります。
この工法は原状回復が必要な物件での使用に適しています。
原状回復できるフローリング
としての
「JIS規格にはない」
重要なポイント
原状回復できるフローリングは、「粘着剤や接着剤を使わない」ことが必要になります。
この場合は下地に対して固定しない、いわゆるフローティング工法になり、
特に以下の3点は重要です。
-

-
粘着剤・接着剤を使わない床材の重要ポイント1
1.フロアタイル同士に段差ができないこと
製品自体が真っすぐでも、下地が湾曲していることはよくあります。そのような場合でも、フロアタイル同士に段差が生じないことが理想的です。
-

-
粘着剤・接着剤を使わない床材の重要ポイント2
2.安定した状態を保つこと
製品自体の寸法や形状が常に一定であることが理想的ですが、これが製品として最も難しい点でもあります。さらに、反りが生じないことも重要な要素となります。
-

-
粘着剤・接着剤を使わない床材の重要ポイント3
3.防水性能
例えば、水をこぼした際に下地へ水が浸透しないこと、また万が一浸透しても簡単に拭き取れることが求められます。
ここからは重要ポイントを
1つ1つ詳しく解説します。

フロアタイル同士に
段差ができないこと
置敷きフロアタイルのJIS規格では、フロアタイルを平面に置いた際、端が最大0.5mmまで浮いても許容されるとされています。これは、0.5mm程度の浮きであれば、粘着剤の力によって抑え込むことができるためです。
一方で、粘着剤を使用しない場合は、1枚の状態で全く反りがないこと、または複数枚を組み合わせた際に段差が解消される構造が求められます。
-

-
自重によって反りを防止する
この方法は、柔軟性のあるPVC(LVT) フローリングに使用されます。フロアタイルが下地の床に沿うように設計されており、「反る力」よりも「重力」が大きくなることで、自然に密着する仕組みです。
一方、SPCフローリングの場合、反り自体は発生しにくいものの、下地に沿わず真っすぐな形状を保とうとする特性があるため、この方法は採用されません。
また、しなやかさも重要ですが、柔軟性を高めるために可塑剤を追加すると、寸法安定性が低下するという課題があります。
-

-
サネによって段差を防ぐ
硬いSPC素材で使用される手法のひとつに、「クリック式」があります。隣り合うフロアタイル同士がかみ合う(篏合する)ことで、段差を完全になくす仕組みです。そのため、クリックの精度が非常に重要となります。
また、PVC素材のクリック式フローリングも存在しますが、PVCはクリック式との相性が良くないため、一般的にSPC素材のほうが適しています。
-

-
表面に面取りを施す
これは、段差を完全になくすのではなく、段差を感じにくくする手法です。単独で使用されるのではなく、「自重による反り防止」や「サネ」との併用によって機能します。
また、柄によっては意匠性の向上効果もありますが、面取りが大きすぎると基材層の色が露出し、かえって意匠性が低下する可能性があります。

安定した状態を保つこと
安定した状態とは、施工後に温度変化、湿度変化があってもフロアタイルとしてのサイズが一定で、反りや湾曲が発生しないことです。
-

-
1.PUコーティング層
薄いため安定性に影響しない
2.PVC耐摩耗層
温度変化による伸縮が大きくコア層との違いで反りの発生原因となる
3.印刷層
紙やPVCが使われ、その素材によっては耐摩耗層と同様に反りの原因となりうる
4.コア層
PVCやSPCが使われ、サイズそのものの変化に大きな影響を与える
5.バッキング層
柔らかい素材であるため、安定性にはそれほど影響しない
樹脂製フロアは、温度変化に対する素材のサイズ変化が大きい素材です。温度変化によりそもそものサイズが変わったり、層毎の伸縮率が違うため、反りとなって現れることがあります。SPC製のほうが炭酸カルシウムを多く含むため、伸縮しにくいと言われていますが、実際はPVC製(LVT)も炭酸カルシウムがSPCと同程度含まれています。伸縮に大きく左右するのはそのフロアタイルを柔らかくする可塑剤の量が大きく左右します。
そもそも吸水しにくい素材であることが多く、湿度の変化についてはあまり考慮しなくてもよいでしょう。
-

-
温度変化に対する伸縮を抑える素材
SPCは、PVC(LVT)に比べて可塑剤の添加量が少ない素材です。そのため、温度変化による寸法変化率も小さくなります。
しかし、可塑剤を含まない分、素材の柔軟性が低く、自重による自己平滑性がないため、反りが発生しやすいという特徴もあります。そのため、SPCフロアタイルは、クリック式などのかん合式が一般的に採用されています。
-

-
ガラスファイバー層を加える
一方、PVC(LVT) は温度変化による寸法変化が大きい素材ですが、PVCのコア層にガラスファイバー層を挟むことで、伸縮を抑えることが可能になります。これは、PVCが膨張しようとする力に対して、ガラスファイバーが寸法を維持しようとする力が働くためです。特に高温時において、フロアタイルの伸びを抑える効果があります。
樹脂はもともと線膨張率が非常に大きい素材ですが、炭酸カルシウムなどを多く含ませることで、その膨張率を抑えています。
理想的な線膨張率とは、本来であれば施工する建物の素材(木造住宅の木材や鉄筋コンクリートなど)と同じ膨張率を持つことです。しかし、木材や鉄筋コンクリートの線膨張率は樹脂に比べてはるかに小さく、炭酸カルシウムを添加しても完全に一致させることはできません。そのため、できるだけ小さい線膨張率であることが理想的とされています。
RESTAでは、多くのSPC製クリック式フローリングとPVC製(LVT) の粘着剤を使わない置敷きフローリングを販売してきました。それぞれの線膨張率は以下の通りです。
SPC製クリック式フローリング:約1.5×10-5
PVC製の粘着剤を使わない置敷きフローリング:約2.2×10-5(8~45℃の平均値)
この数値の製品であれば、施工温度を守り、極端な温度上昇のない室内環境で使用する限り、突き上げなどの問題は発生していません。

防水性能について
ここでいう防水性能とは、製品自体の防水性だけでなく、下地側に水が回らないことも重要な要素となります。水分が下地に回り込み、そのまま放置されると、カビの発生リスクや下地へのダメージが懸念されます。
接着型のフロアタイルの場合、全面に接着剤が塗布されるため、水が回り込む心配は基本的にありません。
-

-
クリック式は水が染み込まない
精度が高く、適切に製造されたクリック式フローリングであれば、接合部の隙間から下地側に水が入り込むことはありません。
ただし、壁際にはクリックによるかん合がないため、そこに水が流れ込むと下地側に浸透する可能性があります。そのため、施工時には壁際の隙間への対策が重要となります。
-

-
クリックがない場合は
部分的に取り外しが可能クリックなどのかん合部分がないフロアタイルの場合、隙間から水が下地側に回り込む可能性があります。
しかし、かん合部分がないことで、部分的に取り外して拭き取ることができる構造となるため、壁際に関してはこの点がメリットとなります。
木質系素材の防水性能
2種類のMDFに水分を滴下して放置した比較
-

防水性のないMDFは水分を吸い込み内部で膨張してそのまま乾燥します。フローリングの場合だと、フィルムの浮き上がりなどが発生します。
-

防水性MDFそもそも水分が浸透せず、表面だけが湿った感じになります。そのため内部の膨張は発生しません。
原状回復が可能なフローリングには、樹脂製だけでなく木質製のものも存在します。しかし、この場合もJIS規格や、木質フローリングの規格である日本農林規格(JAS)には定義がありません。
一般的に、木質製の原状回復フローリングにはMDF(中密度繊維板)が使用されることが多いですが、通常のMDFは水分を吸収しやすく、膨張しやすいという特性があります。そのため、MDF自体に防水性能が備わっていること、または吸水しやすい断面に防水処理が施されていることが必須条件となります。
まとめ
「JIS規格合格品」と記載されている原状回復可能なフローリングは、原状回復に関するJIS規格に合格しているわけではありません。原状回復を前提としたフローリングには、段差が生じない構造であること、温度変化に対して安定していることが必須です。
また、以下のような製品は原状回復の観点から選ばない方が良いでしょう。
■SPCではなくPVC製のクリック式フローリング
- 温度変化による伸縮が大きく、不具合が発生しやすい)
■「伸縮しない」と記載されている
SPCフローリング
- 伸縮しない素材は存在しないため、適切な試験が行われていない可能性がある
■TPRバッキングのフロアタイル
- バッキング材が下地に残る可能性がある
■粘着剤付きフロアタイル
- 剥がすことはできるが、1か月以上使用すると粘着剤が下地にほぼ確実に残る。
- 粘着剤では素材の伸縮を抑えきれず、すき間の発生、突き上げが発生します。
原状回復を重視する場合は、これらの点に注意して製品を選定することが重要です。
原状回復の条件をクリアした
RESTAのDIYフローリング
-
はめ込み式フローリング クリックeuca
置いてはめ込むだけの簡単施工フローリング。段差・隙間なく綺麗に仕上がります。土足でも使用できる優れた耐摩耗性で、キズや汚れが付きにくいのも魅力!幅広いデザインバリエーションからお選びいただけます。
-
置くだけフローリングeuca
裏面に滑り止めが付いており、そのまま置いて並べていくだけの簡単施工です。適度な重みとしなやかさがある床材なので、置くだけで自重によりフラットな状態に。簡単にはがせるので部分張替えも可能!全11種類の幅広い木目柄からお選びいただけます。
引用規格
日本工業規格 JIS A 5705:2016 「ビニル系床材」
日本工業規格 JIS A 5536:2015 「床仕上げ材用接着剤」
日本工業規格 JIS A 1454:2016 「高分子系張り床材試験方法」
フローリングの日本農林規格(JAS):平成25年11月28日農林水産省告示第2903号
© 2025 RESTA. 無断転載を禁じます。
All rights reserved.
公開日
おすすめコンテンツ
PICK UP CONTENTS